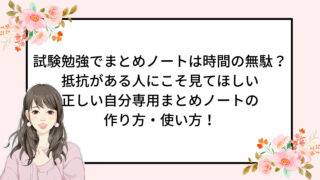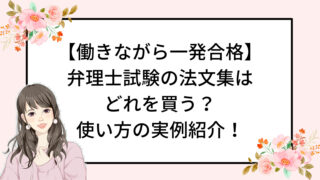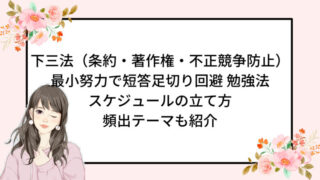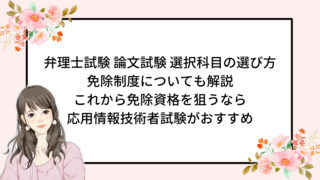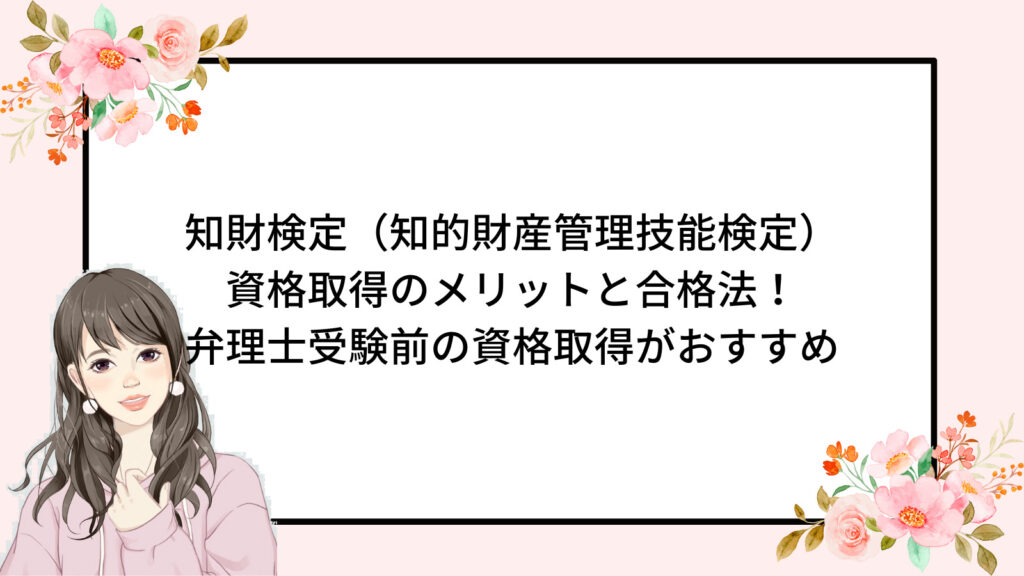
このブログは、知識ゼロの特許初心者だった私が、OLとしてフルタイムで働きながら弁理士試験に一発合格した経験をもとに書いています!!
弁理士試験に挑戦するのはハードルが高いから、まずは知財検定を受けてみようかと思うのですが、どう思いますか?合格すれば何かメリットあるかな?
知財検定は、弁理士試験前に受験するのに適した資格だと思います♥詳しく解説しますね!
- 知財検定はどんな資格?
- 知財検定合格のメリット
- 知財検定の試験概要
- 知財検定に合格するための勉強法
この記事を読むことで、知財検定をとるメリットや具体的な試験概要を知ることができ、受験するかどうかを決心できると思います。
手っ取り早く勉強法だけ知りたいって方はこちらからジャンプできます!
知財検定(知的財産管理技能検定)とは
「知的財産管理技能検定」は知財マネジメントに関する技能の習得レベルを公的に証明するための国家試験です。合格者には「知的財産管理技能士」という国家資格が与えられます。
こんな失礼なTweetをしましたが、知財検定はれっきとした国家資格で政府も、内閣府知的財産戦略本部が策定する「知的財産推進計画」において知的財産管理技能士の資格取得を奨励しています。
「知的財産」と聞くと、小難しいイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、「著作権」や「特許」という言葉は、特に最近ニュースなどでもよく聞くようになりました。実は私たちの周りには知的財産があふれているのです。

知的財産の知識は、メーカーやデザイン・コンテンツ業界で働く人にとってはもちろん必須です。
また近年は、いわゆる「パクリ」や「違法ダウンロード」など特に著作権の問題がニュースになることも多く、上記のような仕事をしている方以外にも重要な知識と認識されており、学生の受験も増えているそうです。
知財検定の累計受験者数は51万人、合格者は14万人を超えているメジャーな資格となりつつあります。
そういう私も弁理士であると同時に「知的財産管理技能士」(3級・2級合格)でもあります!(どや~
「知的財産管理技能士」取得のメリット
日常生活でも役立つ知的財産の基本知識が身に付く
上述したように、私たちの身の回りには知的財産があふれており、知財検定で勉強した基本知識は日常生活でも役に立ちます。
特に著作権は私たちの身近にあり、SNSの使用などで知らないうちに著作権侵害に巻き込まれるようなリスクを避けることができます。
またYouTubeなとでコンテンツ作成を行っている方にとっては自分がどんな権利を有しているかを実感することができ、もしその権利を侵害されたときには適切に対処することができます。
近年、知財意識が高まっており、小説やドラマでも知的財産にフォーカスが当たることが増えています。「下町ロケット」や「それってパクリじゃないですか?」などのドラマ化も話題です。
これらの小説やドラマで焦点の当たっている特許や商標の侵害訴訟などは、関係する業界で働いていないとなかなか身近な感覚は持てませんが、知財検定を通じて知財の基礎を勉強すれば、少し感情移入して見ることができるようになると思います。
ジャニーズWESTの重岡くん効果で、知財を勉強し始める方も増えたりして…と私も期待しています。
合格しやすい資格の割に就職・転職や昇給の面で有利になる
知財検定に合格すれば、知財管理の基礎知識が備わっていることを客観的に示す証明となります。
それが著作物なのかブランドなのか発明なのかは違えど、どの企業にとっても知的財産は重要な資産の一部です。企業は自社の知的財産を守る必要があり、一方で他者の知的財産を侵害しないように尊重しなければなりません。
そのため、人事評価や就職・転職時の採用基準として知的財産管理技能士の資格有無を見る会社が増えています。
実際に私が所属する知財部の中途採用求人票にも、知的財産管理技能士を歓迎する旨記載されています。
▼企業知財部の仕事の記事
もちろん、知財に関係性の深い業種(コンテンツ制作会社・製造業・特許事務所)や部署(知財部・法務部・研究開発部)では高く評価されますが、知的財産に全く関係のない業種や部署は存在しないと言っても過言ではないため、他業種・他部署であってもアピールポイントの1つにはなると考えられます。
それほど就職・転職・人事評価でウェイトが高いにもかかわらず、知財検定3級は合格率が65%~75%です。これは国家資格の中では比較的高い合格率であり、知的財産法を初めて学習する方にとっても比較的合格しやすい水準です。
知財業界への就職や弁理士試験の受験に関する判断材料になる
弁理士と知的財産管理技能士は共に知的財産に関する国家資格です。業務面での大きな違いは、弁理士には特許出願などの手続の代理という独占業務が付与されていることです。
そのため、知財管理技能士よりも弁理士の方が高く評価され、年収も高くなる傾向にあります。
弁理士になるためには通常、弁理士試験に合格する必要があります。弁理士試験は年に1回しか開催されず、合格者の平均勉強時間が約3000時間、合格率は例年1桁%です。
またそのように弁理士試験は難易度が高いので、独学では合格するのが難しく予備校で高額な講座を購入する人が多いです。
ここまでお金と時間をかけても合格できない可能性のある試験は、リスクが高くハードルが高いですよね…
そこで、弁理士試験に挑戦する前に知財検定を受けてみることがおすすめです。弁理士に比べれば時間・費用の両面でリスクが小さくチャレンジしやすいです。
知財初心者にとっては、知財に少し興味を持ったくらいの段階では、自分に知財の勉強や業務が向いているのかまだ判断がつかないと思います。
知財検定の試験範囲は知財法の初歩~基本の内容のため、勉強してみることによって自分が知財に抵抗を持たないか、得意不得意をある程度判断することができます。これによって、弁理士試験を受けてみるか、や知財業界への転職を考えてみるか、の判断にも役立ちます。
また、知財検定の試験範囲は知財法を広く浅くカバーしているので、先に勉強しておくことによって弁理士試験の勉強を始める際に全体像を効率的に把握できます。
実際に私もこの理由で知財管理技能士の資格を取得しましたし、知財管理技能士を経て弁理士になる人は私の周りでも多いです。
しかも、知財管理技能士は、知的財産教育協会が提携する機関のサービスを特別割引価格で利用することができ、その中にはLECやTACといった大手予備校が含まれています!そのため弁理士試験対策講座を受講する際に講座料金が安くなります。
知財検定1級~3級の違い
知財検定は試験の難易度によって1級~3級に分かれており、さらに1級は専門分野によって、「特許専門業務」、「コンテンツ専門業務」、「ブランド専門業務」の3つの分野に分かれています。
ざっくり言うと3級は知的財産の初歩、2級は基本、1級は専門という段階です。
また、3級は誰でも受験可能で、2級も3級合格者であれば受験できるため受験資格がゆるいのですが、1級の受験のためには最低1年以上の実務経験が必要です。
さらに2級・3級は知的財産教育協会から公式テキストが出版されているのに対し、1級にはなく対策が難しい、少しマニアックな試験の位置づけです。
もちろん知財検定に深く興味を持った方が1級を受験するのは素晴らしいことですが、個人的には2級まで取得していれば十分と考えていて、私自身2級までしか持っていません。上述したメリットも2級までの取得で十分享受できます!
知財検定3級の概要
試験日
年3回(3月・7月・11月)
弁理士試験と違って年3回も受験できるのは嬉しいですね…もし落ちてしまってもまた4か月後には受験できる!
試験内容・時間
- 学科試験:筆記試験(マークシート方式 3肢択一式) 45分
- 実技試験:筆記試験(記述方式・マークシート方式併用) 45分
「実技試験」というと何かハードルが高そうに聞こえますが、マークシートではなく記述式の事例問題が出題されるだけです。しかも記述式と言っても長文を書くわけではなく、日付や単語を解答するものがほとんどなので安心してください。
受験地
北海道から沖縄まで全国各地 20か所以上
※ CBT方式の追加導入により試験実施地区が拡大しています。詳細はこちら
受験料
- 学科試験 6,100円
- 実技試験 6,100円
受験資格
- 知的財産に関する業務に従事している者または従事しようとしている者
- 3級知的財産管理技能検定の学科または実技いずれか一方の試験のみの合格者
つまり、年齢や職業問わず誰でも受験することが可能です。
過去問題
公式HPに過去3回の検定の試験問題と正解が公開されています。
試験勉強の時には、後述の厳選過去問題集が便利です。
合格基準
- 学科試験 満点の70%以上
- 実技試験 満点の70%以上
合格率
最近は65%~75%で推移しています。
知財検定2級の概要
試験日
年3回(3月・7月・11月)
試験内容・時間
- 学科試験:筆記試験(マークシート方式 4肢択一式) 60分
- 実技試験:筆記試験(記述方式・マークシート方式併用) 60分
受験地
北海道から沖縄まで全国各地 20か所以上
※ CBT方式の追加導入により試験実施地区が拡大しています。詳細はこちら
受験料
- 学科試験 8,200円
- 実技試験 8,200円
受験資格
以下のいずれかに該当する者
- 知的財産に関する業務について2年以上の実務経験を有する者
- 3級知的財産管理技能検定の合格者
- 大学又は大学院において検定職種に関する科目について10単位以上を修得した者
- ビジネス著作権検定上級の合格者
- 2級知的財産管理技能検定の学科または実技いずれか一方の試験のみの合格者
3級に合格してから受けられる方が多いと思います。実務経験や大学で知財について学んでいる方は、いきなり2級から受験するのも良いですね。
私自身はまだ実務経験が1年たってないうちだったので3級から順番に受験しました!
過去問題
公式HPに過去3回の検定の試験問題と正解が公開されています。
試験勉強の時には、後述の厳選過去問題集が便利です。
合格基準
- 学科試験 満点の80%以上
- 実技試験 満点の80%以上
合格率
最近は30%~50%で推移しています。
知財検定の申し込み方法
お申し込みはこちらから。
次は第52回で2025年11月16日(日)に開催されます!申込期限は10月7日(木)です。
3級と2級は併願できませんのでご注意ください。
それぞれの級の学科と実技試験は併願できるので一気に合格するのがおすすめです。一度に申し込みましょう。
知財検定に合格するための勉強法
知財検定3級・2級は独学でも十分合格可能
弁理士試験のように、知財検定合格のためには予備校や通信講座を受講する必要があるのでしょうか?
3級・2級は、予備校や通信講座を受講しなくても独学で合格可能と考えます。弁理士試験のように知的財産法の詳細な条文や判例・審査基準などの知識は必要なく、大枠の基本的な内容からの出題が多いためです。
知財検定3級の合格のために必要な勉強時間を調べてみると約50時間、その後2級の合格のためにはさらに約20~40時間と書かれている情報が多かったです。(知財検定3級と2級の試験範囲には重複部分が結構あります)
弁理士試験の合格者平均勉強時間(約3000時間)と比べるとその容易さがわかりますね笑
個人的にはもう少し短い勉強時間でも合格できる感覚です。私自身、知財法初心者の時に受験しましたが、結局どちらも1週間程度で詰め込んだ記憶があります。確か勉強にかけられた時間はそれぞれ20時間くらいでしたが合格できました。
これから知財法を日常生活や実務で生かそうと考えている方は、私のように一夜漬けせず、50時間程度を確保して勉強を始めてくださいね…笑
知財検定3級・2級の独学での勉強法
知財検定3級・2級合格のために使う教材
独学の勉強法は、3級・2級ともに公式テキストの内容を暗記+過去問演習のみで十分です。
2級は公式テキスト以外にも、より条文・判例・審査基準などの詳細にフォーカスした市販の教材が存在します。しかし、試験に合格するという目的であれば公式テキストのみで十分です。
法改正の影響があるため、公式テキストも過去問集も必ず最新版を購入してくださいね。
▼知的財産教育協会の公式テキスト(最新)はこちらです。
- 3級
- 2級
過去問集は複数種類市販されていますが、私が使っていたのはアップロード知財教育総合研究所のものです。
公式テキストの目次に合わせた体系別に問題が収録されており、分野ごとの学習が効率的に行えます。
もちろん、最新の法改正を踏まえた丁寧な解説付きです。
▼アップロード知財教育総合研究所の過去問題集(最新)はこちらです。
- 3級
- 2級
知財検定3級・2級合格の具体的な勉強方法
知財検定の勉強においても、私がおすすめするのは変わらず「アウトプット→インプット勉強法」です。
知財検定における「アウトプット→インプット勉強法」において、もちろん自分専用まとめノートを作成しても良いのですが、私は公式テキストへの追記で代用していました。
知財検定の試験範囲となるのは、公式テキスト1冊だけで情報を一元化する必要がなかったこと、公式テキスト自体がイラストや表を多用しており暗記しやすい形にすでにまとまっていたことが理由です。
そのため、具体的には下記の4ステップで勉強を進めました。
- 公式テキストを一通り読んで試験範囲の全体像を正しく理解する
- 公式テキストを見ながら過去問題集を解く
- 解けなかった問題に関する情報を公式テキストに追記する
- 追記された公式テキストを暗記する
仕上げに時間感覚を掴むために、本試験と同形式の実力テスト(過去問題集に付属)を時間を計って解いてみました。でも多くの方は時間が余ると思うのであまり必要ないかも!
試験範囲の中でも特許法・著作権法は出題数が多いので重点を置いて勉強することで得点率を高めることができます。
受験生の中でもこの2分野のどちらかに興味を持って受験している方が多いと思います。
ちなみに私は独学で、知財検定3級・2級それぞれ一発合格したよ!(どや~その2
効率よく短い勉強時間で合格したいなら通信講座を活用
知財検定は公式テキストがわかりやすく初心者であっても読めば内容を理解できるようになっていますし、試験自体もそれほど難易度が高くなく合格率も高い(しかも落ちてもまた4か月後に挑戦できる)ため、個人的には独学で受験するのがおすすめです。
しかし、必ず次の試験で確実に合格しないといけない事情がある方や、やっぱり自分でテキストを読むのではなく解説の授業を受ける方が頭に入りやすいという方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、各社予備校や通信講座を活用するのも一案です。これらを活用することで、試験に出やすい分野・出にくい分野を知り効率的に勉強でき、プロの解説を聞くことでより体系的に知識を定着させることができます。
知財検定の講座を用意している予備校・通信講座を下記にまとめました。
| 公式サイト | TAC | 資格スクエア | スタディング | |
| 3級 | 3級対策講座 19,000円 約14時間 | 3級オンライン本科生 22,000円 約15時間 | ー | 3級合格コース 約5時間 |
| 2級 | 2級対策講座 33,000円 約25時間 | 2級オンライン本科生 41,800円 約24時間 | ー | 2級合格コース 約6時間 |
| 3級+2級 | 3・2級対策セット講座 49,000円 約39時間 | ー | 3級・2級まとめて対策講座 約25時間 | 3級・2級セットコース 約11時間 |
※各講座の金額は標準価格で、キャンペーンによってさらに安くなる可能性があります。
資格スクエアは3級向け・2級向けと講座が分かれていないため、3級にフォーカスしたい方は、スタディングの3級合格コースがおすすめです。
3級・2級両方に合格を目指している方は、資格スクエアの3級・2級まとめて対策講座の方がおすすめです。弁理士試験対策講座でも同様ですが、資格スクエアの講座のコストパフォーマンスは素晴らしいためです。
独学でも合格できる試験の対策のため、頻出分野の情報を得ることと、講師の説明を受けて体系的に学習すること自体が重要だと考えています。
そう考えると、いずれの講座もそのポイントは押さえており、各講座の質の差はそれほど大きくないです。正直どの講座を受講しても合格にはかなり近づくと思うのでコスパで選ぶのが得策と思います。
個人的には3万円以上は抵抗があるので、私なら資格スクエアかスタディングを選びます!
知財検定まとめ
知財検定に合格したら次は是非弁理士試験に挑戦してみてください。
弁理士試験は知財検定と違って独学での短期合格はまず難しいので、予備校・通信講座を受講しましょう。よければ下記の記事を参考にしてくださいね。
また知財業界に興味を持たれたら一度転職も検討してみてください!転職サイト・エージェントへの登録は無料です。
ご質問があれば、コメント、お問い合わせページ、TwitterのDMからお気軽にどうぞ♥
また、新着記事更新時などTwitterで発信しますので是非フォローもよろしくお願いします!
さくら🌸

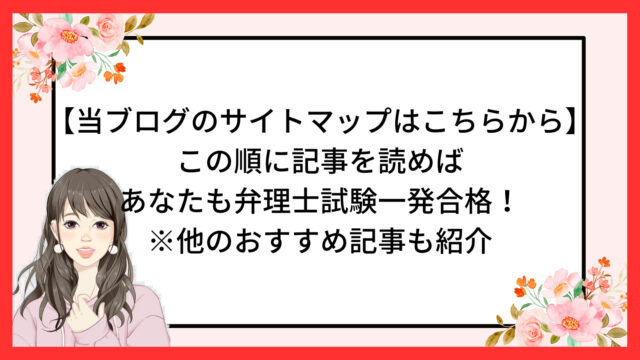
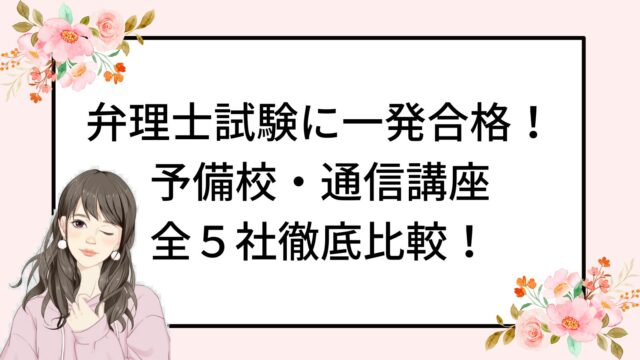
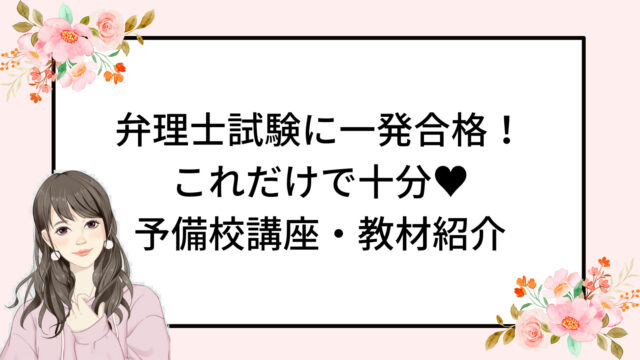
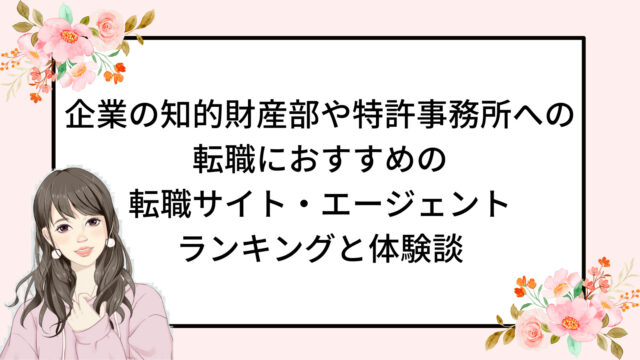
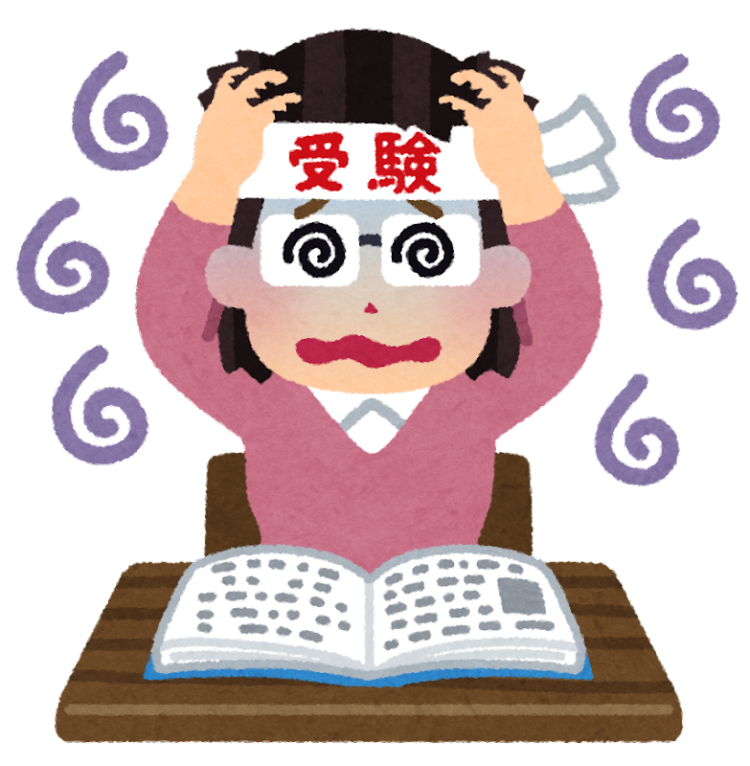


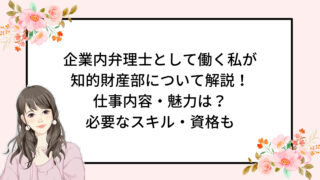

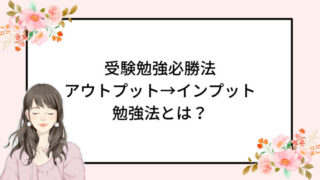
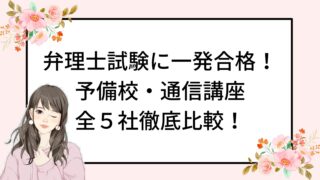
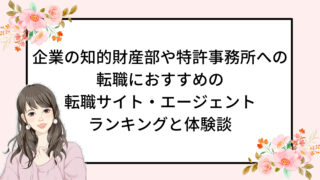
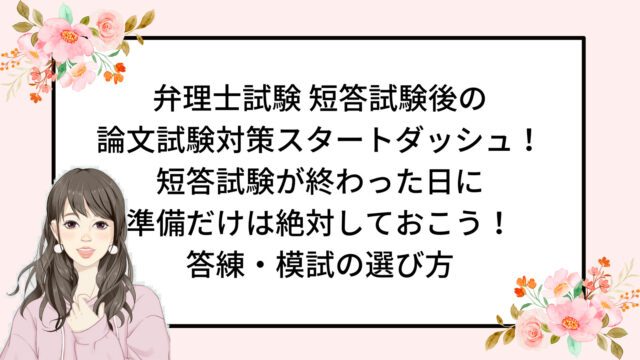
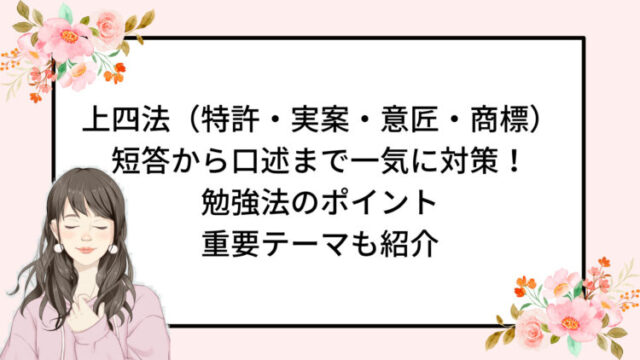
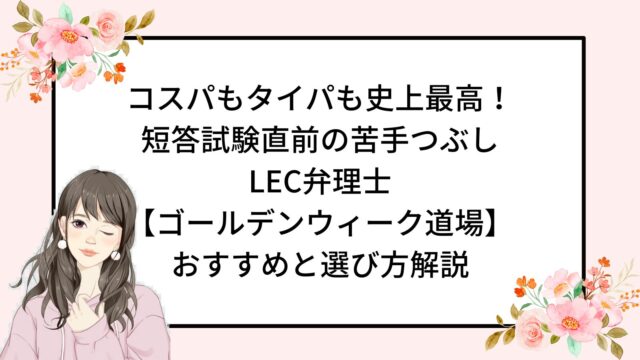
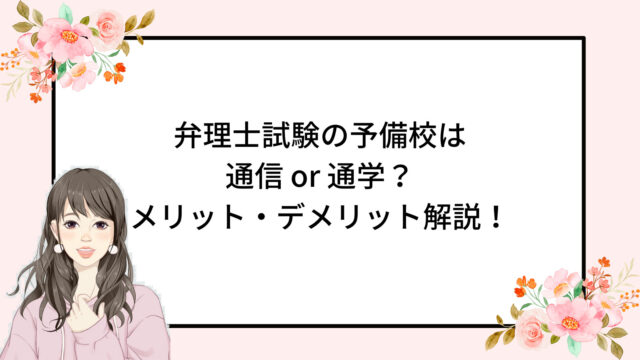
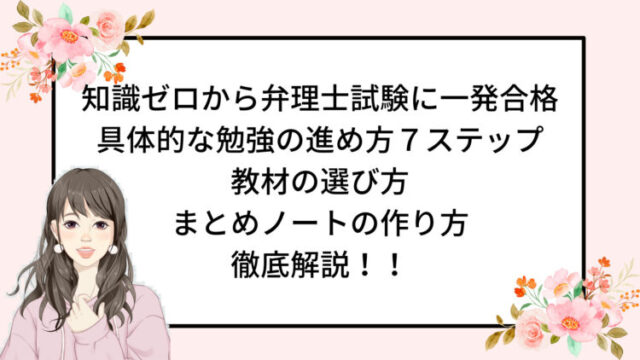
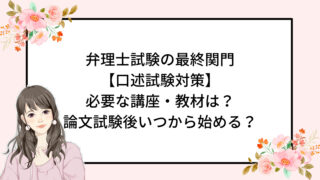
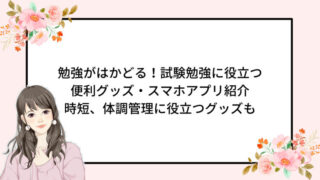
 LEC
LEC 
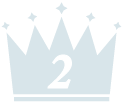 資格スクエア
資格スクエア 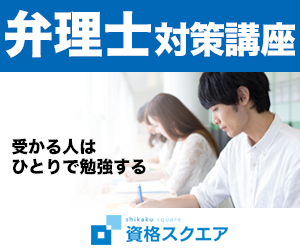
 アガルート
アガルート